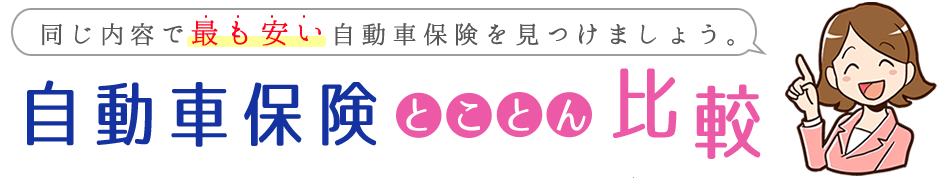自動車共済とは?一般的な自動車保険との違いを徹底比較!
| 執筆者 | |
|---|---|
 |
ファイナンシャルプランナー:小澤 美奈子 |

自動車に付ける補償(保障)と言えば、「自動車保険」を想像する人が多いと思います。しかし「自動車共済」や「マイカー共済」というような共済も、選択肢の一つとして考えられます。
しかし多くの方は共済がどういう仕組みなのか? 誰でも入れるのか? 色々疑問が沸いてくるのではないでしょうか?
それもそのはず。実際に自動車保険と自動車共済に加入している人の割合を比較すると、圧倒的に自動車保険の加入割合が多いという結果が出ています。
| 自動車共済 | 自動車保険 | |
|---|---|---|
| 加入率 | 13.7% | 74.1% |
※出典:損害保険料率算出機構 「自動車保険の概況」(2016年度)
このように加入率はさほど多くない自動車共済について、自動車保険との違いや、補償(保障)内容について、まずは全労済とJA共済を中心に確認していきましょう。
自動車共済と自動車保険の違いを比較
ここでは自動車共済と自動車保険の違いを比較しながら、確認していきます。
まず両者の大きな違いとしては、業務の内容の規制や罰則等を定めている法律が異なる点が挙げられます。自動車保険は「保険業法」、JA共済は「農業協同組合法」、全労済には「消費生活協同組合法(生協法)」が適用されています。
ただし、契約当事者間における契約ルールについて定めている「保険法」については、自動車保険と共済の両方に適用される仕組みです。
また、自動車保険と共済では監督する省庁にも違いがあり、自動車保険は「金融庁」、共済の中で全労済は「厚生労働省」、JA共済は「農林水産省」となります。
さらに自動車保険の場合は、契約を締結することにより誰でも加入できますが、共済の場合は、営利を目的としない相互のたすけ合いを目的とし、特定の職業に属している人を対象としている組織と、A共済のように出資金(1,000円からが多い)を支払うことで誰でも加入できる共済の二つに分かれています。
補償(保障)内容について
自動車共済では、自家用車を対象とした補償(保障)が中心となり、対人、対物、人身傷害など、自動車保険とほぼ遜色のない補償(保障)を兼ね備えています。基本的には、シンプルで選びやすい商品設計となっています。
事故対応について
事故受付時間については、ほとんどの共済で24時間365日対応しています。
全労済の「マイカー共済」では、「事故初期対応を19時までに連絡あった場合に、土日祝日含めた9時から21時までサポートが受けられる」とあり、共済でも損害保険会社の自動車保険並みのサービスが受けられるようです。
ただし、事故に遭い自走不能となった場合のレッカーけん引サービスなどは、損害保険会社の自動車保険商品では「最寄りの指定修理工場までは無料」としているところが多い中、共済商品では「30キロまで無料」や、「15万円限度」としているところが目立っています。
等級の取り扱い
共済における等級制度は、全労済では「1から22等級」、JA共済では「1から20等級」まで設けているなど、自動車保険の等級制度とほとんど変わりません。もちろん、自動車保険から共済への等級継承も可能です。
また一部の共済の中には、事故が遭った場合に適用される「事故あり等級制度」を設けていないところがあり、そのような共済に加入すれば、事故による保険料値上がりリスクが減ることになります。
車両保険について
全労済では、車両事故を総合的にカバーする「一般補償」の他、車対車の事故の補償をメインとした「エコノミー」などを揃えています。
またJA共済では、全てのリスクに対応する「全損害担保」と、相手自動車との衝突・接触など限定された事故損害を保障する「損害限定担保」の2種類が販売されています。
どちらも自動車保険商品とほとんど遜色ないと思われますが、自動車保険商品で多く見られるような細かい補償の取り外しや、自己負担額(車両免責金額)の設定が自由にできない点などに、多少の見劣り感は否めません。
公務員や教職員の共済について
教職員や公務員が加入できる主な自動車共済について確認しましょう。
- 教職員・・・教職員共済
- 国家公務員・・・国公共済会
- 市役所の職員・・・全国都市職員災害共済会
これらの共済の大きな特徴は、対象の団体等に属した職員しか加入できないことです。つまり、その団体に属していない一般の人は入れないことになります。
次にそれぞれの特徴を挙げていきます。
教職員共済
教職員共済については、人身傷害補償付きのコースと無しのコースのどちらかから選ぶというシンプルな設計となっています。また等級については、1~20等級まであり、他社からの等級継承も可能です。
中でも「事故あり等級」制度を設けていないは特徴的です。車両については、車両共済として損保ジャパン日本興亜の車両保険を適用しています。
全国都市職員災害共済会
全国都市職員災害共済会の自動車共済の大きな特徴は、等級制度を設けていない点です。つまり事故を起こしたとしても、保険料が変わらないことになります。
国公共済会
国公共済会は、日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)が1991年に設立した共済事業団体で、国公労連の組合員が会員になることができます。
自動車共済の補償内容としては、車両保険も含め、ほぼ自動車保険商品と変わらない充実した内容となっています。また等級についても、1~20等級まであり、こちらも他社からの等級継承ができます。
まとめ
当コラムを読むとお分かりの通り、共済といえども、さまざまな組織や組合が存在します。中には特定の団体に属していると、そこに関連した自動車共済に加入することで「団体割引」が適用される場合もあります。
一昔前は、自動車共済は保険料が安いと言われていたようですが、昨今においてはネット損保などの台頭により、必ずしも自動車共済が安いと言い切れなくなってきました。
大事なのは、保険料のみならず、補償内容も含めて複数の商品を比較して、自分に合う商品を選ぶことだと言えます。
保険料を安くする簡単な方法!
同カテゴリ「自動車保険を比較で安く!」内の記事一覧
- 安いと噂の自動車保険20社比較してわかった最安値はココ!
- 私が自動車保険料を比較して3万円安くした証拠画像と解説
- 保険料が安くなる自動車保険の割引制度を比較
- スポーツカーの自動車保険を比較で安くする方法
- 18歳~20歳の自動車保険を安くする5つの方法を比較!
- 必見!比較でわかる自動車保険が安くなる年齢
- 自動車共済とは?一般的な自動車保険との違いを徹底比較!
- 18歳(10代)が1番安い自動車保険徹底調査!
- 21歳(20代)が1番安い自動車保険徹底調査!
- 26歳(20代)が1番安い自動車保険徹底調査!
- 30歳(30代)が1番安い自動車保険徹底調査!
- 40歳(40代)が1番安い自動車保険徹底調査!
- 50歳(50代)が1番安い自動車保険徹底調査!
- 60歳(60代)が1番安い自動車保険徹底調査!