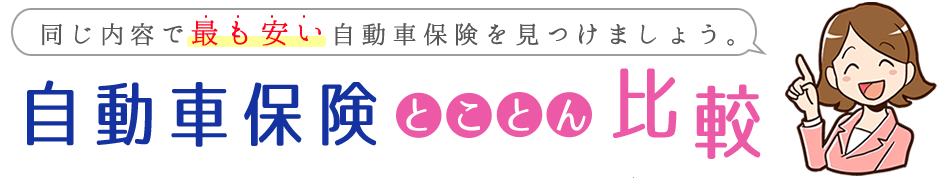等級が下がると自動車保険料はどのくらい変わる?3等級ダウン!プロFPが解説!
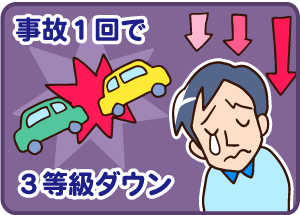
自動車事故を起こしてしまった場合、自動車運転歴に事故歴が付されてしまう他、自動車保険を使用した場合には原則として翌年度から支払う自動車保険料が高くなります。
仮に優良ドライバーの証であるゴールド免許はブルー免許へ、自動車保険の最高等級である20等級は17等級へ格下げになります。このようになってしまった場合、自動車保険料の負担はどの程度上がってしまうのか気になりませんか?
もし保険料が高くなりそうだったら、
こちらから安い保険を探すことができます。
今回はお金の専門家であるFPが概算イメージシミュレーションを行い、そこから見えてくるもの、考えられるものを広い視野でご紹介していきます。
目次
等級の格下げには一定のルールがある。3等級ダウン!

自動車保険料が決定される要因の1つに「等級」がありますが、この等級が交通事故などで格下げになるには一定のルールがあります。まずは、そこから確認していきましょう。
等級格下げのルール
- 1. 等級の格下げは、保険事故1件につき「3等級」下がります
- 2. 偶発的な原因で自動車保険を使った場合、「1等級」下がることがあります
等級の格下げは「保険事故」1件につき3等級下がります。わかりやすく説明すると、交通事故を起こしたとしても自動車保険を使用しなければ等級は下がらないということです。「交通事故」ではなく「保険事故」となっているのはそのような意味があります。
どんな場合に「保険事故」になるの?
保険事故とは、その名のとおり保険を使うことになった事故を指しますが、保険と一口に言っても、自動車保険にはさまざまな補償や特約があります。
その中でも、3等級ダウンするのは主に「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」のいずれかを使った場合です。これら3つは、いわゆる「基本補償」と呼ばれます。
ただし車両保険の場合、それが「偶発的な原因」によるものであれば、例外的に1等級ダウンとなります。
また、下のほうでもくわしくご説明しますが、契約者自身に過失がない「もらい事故」などで車両保険を使った場合は、等級が一切ダウンしない「ノーカウント事故」として扱われます。
基本補償以外のオプション補償やロードサービスなどは、利用しても等級に影響ない場合がほとんどですが、一部の特約では1等級ダウンすることがあります。
偶発的な原因っていったい何?
偶発的な原因で自動車保険を使った場合、1等級下がると書かれていても「それって何?」と思ってしまいます。
実のところ数年前は「等級据え置き事故」といって自身に過失がない偶発的な自動車の損害は自動車保険を使用しても等級に変化がありませんでした。
しかし、2013年4月1日以降において「等級据え置き事故」が廃止され、以下のリストにおける自動車損害で保険を使用した場合には、翌年度は1等級格下げになります。
偶発的な原因一覧
- 1. 火災または爆発による自動車損害
- 2. 盗難による自動車損害
- 3. 騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為または破壊行為による自動車損害
- 4. 台風、竜巻、洪水、高潮による自動車損害
- 5. 飛来中または落下中の他物との衝突による自動車損害
- 6. いたずらによる自動車損害
- 7. 落書または窓ガラス破損による自動車損害
例えば、飛び石が原因でフロントガラスにひびが入ってしまった場合を考えてみましょう。これは筆者の実体験なのですが、高速道路を走行中、飛び石がフロントガラスに接触し目でわかる程度の傷がついてしまいました。
大したことはないと思っていたのですが、専門家から言わせると、これが原因でフロントガラスが大破するなどは一般的にあり得るようです。
しぶしぶ交換することにしましたが、これは上記リストの「5. 飛来中または落下中の他物との衝突による自動車損害」に該当し、自動車保険を使用して修理した場合、翌年度は1等級格下げになります。
自動車損害の状況や修理費用と相談しながら保険を使用するかしないかを決めることが大切になります。
文章はまだ続きますが、車の保険料が気になった方は先に一括見積しておくと読み終わったころに続々と保険料が送られてきます。お手元に車検証か保険証券のご準備を!入力はたったの5分程度です。
ただいまキャンペーン中

等級が下がるだけじゃない!「事故有係数」とは
保険事故による等級の引き下げは、昔から行なわれていたことですが、2013年10月から新たに「事故有係数」の制度が導入されました。
事故有係数とは、事故を起こした人だけに適用される保険料の割引率です。
それまでは、同じ等級であれば事故の有無にかかわらず一律の割引率が適用されていたところ、現在は同じ等級でも「無事故等級」と「事故有等級」の2つに分かれ、事故を起こした人の割引率のほうが低くなりました。
たとえばソニー損保では、2018年3月現在、等級ごとに以下のような割増引率を採用しています。

このように、同じ等級でも無事故の人と事故ありの人では、保険料の割引率に差があります。等級によっては20%近くの開きがありますから、かなりの保険料差になるはずです。
保険事故を一度でも起こすと、次の更新時から事故有係数が適用されてしまうため、この制度が導入されてからは保険金の請求に慎重になる人が増えたといわれています。
事故有係数が適用される期間はいつまで?
事故有係数は、一度事故を起こしたらずっと適用され続けるわけではありません。
事故有係数が適用される期間(事故有係数適用期間)は、以下のように決まっています。
| 3等級ダウン事故の場合 | 次年度から3年間 |
|---|---|
| 1等級ダウン事故の場合 | 次年度から1年間 |
たとえば20等級の人が3等級ダウン事故を起こした場合、その後の等級と割引率は以下のようになります(割引率は前出のソニー損保のものを採用しています)。
| 現在 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 無事故等級 | 20等級 (63%割引) |
― | ― | ― | 20等級 (63%割引) |
| 事故有等級 | ― | 17等級 (38%割引) |
18等級 (40%割引) |
19等級 (42%割引) |
― |
一度等級が下がっても、その後事故を起こさない限り1年ごとに1等級ずつアップしていきます。
1等級ダウン事故を1回起こしただけなら、事故有係数が適用されるのは次の年だけで、2年後には再びもとの等級にもどれるということです。
2年連続で保険事故を起こした場合
もし2年連続で保険を使う事故を起こした場合、事故有係数適用期間はどうなるのでしょうか?
ここでは、不幸にも3等級ダウン事故を2年連続で起こした場合についてシミュレーションしてみます。カッコ内は割引率です。
| 現在 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無事故 | 20等級 (63%) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 19等級 (55%) |
| 事故有 | ― | 17等級 (38%) |
14等級 (31%) |
15等級 (33%) |
16等級 (36%) |
17等級 (38%) |
18等級 (40%) |
― |
2年連続で3等級ダウン事故を起こした場合、2年連続で3等級ずつ引き下がってから、また1等級ずつ上がっていくことになります。
ちなみに、事故有係数適用期間の上限は6年間と決まっていますので、もし3年連続で事故を起こした場合でも、7年後には無事故等級にもどることになります。
1年のうちに2回事故を起こした場合
最後に、同じ年のうちに2回事故を起こしたケースについてもご紹介します。
確率は低いですが、20等級の人が1年で3等級ダウン事故を2回起こした場合の等級と割引率は、以下の通りです。
| 現在 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無事故 | 20等級 (63%) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 20等級 (63%) |
| 事故有 | ― | 14等級 (31%) |
15等級 (33%) |
16等級 (36%) |
17等級 (38%) |
18等級 (40%) |
19等級 (42%) |
― |
1年のうちに3等級ダウン事故を2回起こすと、単純に「3×2」で6等級ダウンすることになります。その後は無事故なら、1年ごとに1等級ずつアップしていきます。
1年のうちに3等級ダウン事故と1等級ダウン事故を起こした場合は、「3+1」で4等級のダウンです。
保険を使っても等級が下がらない事故とは?
保険加入者にとっては手痛い等級ダウンですが、実は保険金が支払われても等級に影響しないケースも少ないながらあります。いわゆる「ノーカウント事故」と呼ばれるものです。
ノーカウント事故になるのは、基本的に「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」のいずれも使用しなかったケースです。
たとえば「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「弁護士費用特約」「ファミリーバイク特約」などの保険金のみが支払われた場合は、ノーカウント事故となります。等級に影響はありませんので、そのまま無事故であれば翌年は1等級アップです。
一方、「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」を使用した場合は、原則として等級が引き下げられます。
ただし車両保険の場合、契約者自身に過失がなければ、「車両保険無過失事故特約」によってノーカウント事故になります。
車両保険の無過失事故特約とは、契約者に過失がない「もらい事故」などで車が損傷した場合、等級ダウンせずに車両保険が支払われるという契約です。車両保険には必ず自動セットされています。
新しい自動車保険に乗り換えれば、事故有係数適用期間はリセットされる?
上でご説明したように、保険事故を起こすと一定期間、事故有等級のステージに移行し、無事故の人より保険料が高くなってしまいます。
そこで、「次の更新時にほかの自動車保険に乗り換えれば、リセットされるかも」と考える方もいるかもしれません。
しかし、残念ながら保険会社を変えても「等級」と「事故有係数適用期間」はいずれも引き継がれます。たとえば3等級ダウン事故を起こした翌年に別の自動車保険に乗り換えても、やはり3年間は事故有係数が適用されるのです。
ただし、もともとの保険料は保険会社によって異なりますので、等級ダウンで保険料が上がってしまった方は、これを機に保険を見直してみることをおすすめします。
3等級ダウン事故と保険料増額、概算イメージシミュレーション開始!
ここからいよいよ本題である等級の格下げによる自動車保険料の概算イメージシミュレーションを行っていきます。
今回は最高等級である20等級から17等級へ格下げになったパターン、偶発的な事故で20等級から19等級へ格下げになったパターン、17等級から14等級へ格下げになったパターンの全3パターンをご紹介していきます。
なお、表における青の塗りつぶしは「格下げになったパターン」黄色の塗りつぶしは「無事故のまま経過したパターン」を表しております。
20等級から17等級へ格下げになったパターン
| 年 | 等級 | 概算保険料 イメージ |
等級 | 概算保険料 イメージ |
|---|---|---|---|---|
| 次年度 | 事故あり 17等級 |
50,000円 | 無事故 20等級 |
30,000円 |
| 2年後 | 事故あり 18等級 |
49,000円 | 無事故 20等級 |
30,000円 |
| 3年後 | 事故あり 19等級 |
47,000円 | 無事故 20等級 |
30,000円 |
| 4年後 | 無事故 20等級 |
30,000円 | 20等級 | 30,000円 |
| 合計金額 | 176,000円 | 120,000円 | ||
参考 ソニー損保ホームページより筆者シミュレーション
自動車保険を一度使用したことによって、最高等級に達する4年間の支払保険料に56,000円もの差が生じる結果となりました。長い目で見ると、一度自動車保険を使用することで1年分以上の保険料の違いになることがわかります。
偶発的な事故で20等級から19等級へ格下げになったパターン
| 年 | 等級 | 概算保険料 イメージ |
等級 | 概算保険料 イメージ |
|---|---|---|---|---|
| 次年度 | 事故あり 19等級 |
47,000円 | 無事故 20等級 |
30,000円 |
| 2年後 | 無事故 20等級 |
30,000円 | 無事故 20等級 |
30,000円 |
| 3年後 | 無事故 20等級 |
30,000円 | 無事故 20等級 |
30,000円 |
| 4年後 | 無事故 20等級 |
30,000円 | 20等級 | 30,000円 |
| 合計金額 | 137,000円 | 120,000円 | ||
参考 ソニー損保ホームページより筆者シミュレーション
こちらは偶発的な事故において自動車保険を使用した結果になります。結果として17,000円程度の差が生じておりますが、筆者の体験談のように将来的な自動車の活用を考慮した時、修理した方が良いという場合には思い切って活用してみるのも一策です。
17等級から14等級へ格下げになったパターン
| 年 | 等級 | 概算保険料 イメージ |
等級 | 概算保険料 イメージ |
|---|---|---|---|---|
| 次年度 | 事故あり 14等級 |
73,000円 | 無事故 18等級 |
49,000円 |
| 2年後 | 事故あり 15等級 |
71,000円 | 無事故 19等級 |
48,000円 |
| 3年後 | 事故あり 16等級 |
68,000円 | 無事故 20等級 |
39,000円 |
| 4年後 | 無事故 17等級 |
50,000円 | 無事故 20等級 |
39,000円 |
| 合計金額 | 262,000円 | 175,000円 | ||
参考 ソニー損保ホームページより筆者シミュレーション
ご紹介した3つのパターンの中で最も保険料差額が大きい結果となりました。ここでは仮に17等級での保険料を5万円としてシミュレーションしましたが、4年経過後の差額は87,000円も生じる結果となっています。
事故が起きた場合、保険を使うか使わないかの判断基準は?

上でシミュレーションしたように、等級がダウンすると保険料は明らかに高くなってしまいます。人によっては年間5万円以上アップすることもあるほどです。
そこで、事故を起こした際には「保険を使うべきかどうか」を慎重に考えることが大切になってきます。事故の内容はさまざまですので一概にはいえないのですが、基本的には以下の手順を踏んで検討してみてください。
- ①自己負担金(修理代など)の見積もりを依頼する
- ②来年度から3年分の保険料を試算する
- ③自己負担金と保険料を比較する
自動車保険を使うかどうか判断に迷うのは、おもに他人の物や自分の車を壊してしまった時です。
対人の場合、自賠責保険の限度額内で示談できれば任意保険を使わずに済みますし、限度額を大きく超えるような事故を起こした場合は、迷わず任意保険を使う必要があります。
一方、物損事故や自損事故の場合は、保険を使うかどうか悩みどころです。修理代や賠償金が高額な場合は迷う余地がありませんが、そうでなければ自腹を切ったほうが等級ダウンせずに済み、来年以降の保険料が上がることもなくなります。
一般的には「10万円」がひとつの目安といわれますが、正確な自己負担額を知るためにも、まずは修理工場やディーラーなどに修理代の見積もりをとることが先決です。
さらに、保険会社に保険料の試算を依頼します。ここで知りたいのは、「保険を使った場合の保険料と、使わなかった場合の保険料の差額」です。
3等級ダウン事故を起こした場合は、次年度から3年間保険料がアップしますので、向こう3年間の保険料を計算してもらいましょう。
金額が出たら、自己負担金と保険金の差額を比べて判断します。もし3年間の保険料の差が12万円だった場合、修理代がそれ以下で済むなら自腹を切ったほうがお得です。逆に修理代のほうが明らかに高くつく場合は、保険を使ったほうがいいということになります。
また、車両保険に免責金額を設定している場合は、保険金とは別に自己負担が発生しますので、それも合わせてよく検討してみてください。
等級が下がっても、保険料が高くならない唯一の方法とは!?
ここまでご説明したように、保険事故を起こすと原則3等級ダウンし、3年間は事故有係数が適用されます。
つまり、事故前の等級にもどるためには3年かかりますので、その間地道に無事故を守らなくてはいけません。
ただし、等級が下がっても保険料が高くならないかもしれない方法が1つだけあります。
それは、自動車保険を乗り換えることです。
新しい保険に乗り換えても、等級や事故有係数はしっかりと引き継がれるのですが、そもそもの保険料は各社によって異なります。したがって、今入っている保険よりも保険料が安いところを選べば、等級ダウンの影響を最小限に抑えられるのです。
たとえば、このページでもご紹介している「保険の窓口 インズウェブ」という
一括見積サイト
では、サイトを利用して自動車保険を乗り換えた人の約42%が、年間の保険料を30,000円以上安くすることに成功していると発表しています。
しかも、19%の人は50,000円以上安くなっているのです。これなら、むしろ等級がダウンする前よりも安くなる可能性があります。
保険を使って等級が下がってしまった方こそ、次年度からの保険はしっかりと見直すべきです。
まとめ
20等級から17等級へ格下げになったパターンでは差額56,000円、偶発的な事故で20等級から19等級へ格下げになったパターンでは差額17,000円、17等級から14等級へ格下げになったパターンでは差額87,000円というシミュレーション結果になりました。
交通事故などで自動車保険を使用する影響は事故前の等級に上がるまで大きいことが結果からわかります。
また、現状の等級によって一度自動車保険を使用した場合の保険料差額が大きくなることも確認できます。
支払保険料を考える上で等級と自動車保険料の関係は切り離して考えることはできません。安全運転を常に励行することはもちろんですが、自動車保険を使用するかしないかの判断も重要になってきます。
基本的には、「来年以降アップする保険料<自己負担金」となった場合は、保険を使ったほうがお得ですが、「プラス5万円くらいなら自腹を切る」という人もいますし、逆に「自己負担したほうが得だけれど、今修理代を払ったら当面の生活が苦しくなるから保険を使う」という選択をする人もいます。
もし保険を使うことにした場合は、来年度以降の保険料アップは避けられませんので、できるだけ保険料の安い自動車保険に乗り換えるのも一つの方法です。
等級や事故有係数適用期間はそのまま引き継がれますが、もともとの保険料が安いところに乗り換えれば、来年以降の負担を減らせる可能性があります。