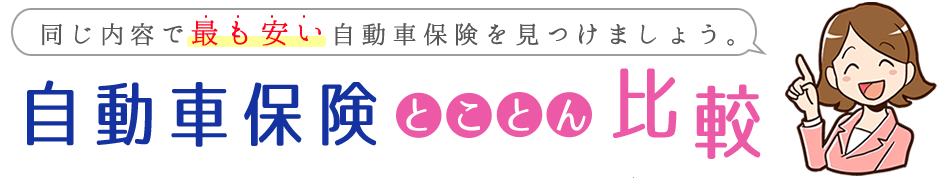軽自動車とコンパクトカーの保険料はどれぐらい違う?
| 執筆者 | |
|---|---|
 |
ファイナンシャルプランナー:阿部 亮子 |
近年の軽自動車の進化とコンパクトカーの手軽さから、どちらのタイプも人気があります。
全国軽自動車協会連合会と日本自動車販売協会連合会によると、2017年12月の新車販売台数は、軽自動車は101,936台、小型乗用車(コンパクトカー)は103,569台となっており、どちらもほぼ変わらない販売台数となっています。
車の維持費には、自動車税や車検費用そして自動車保険などがあります。
その中でも任意で加入する自動車保険は、ネット損害保険会社も多くあり、そのサービスも様々です。
今回は、人気のある軽自動車とコンパクトカーの損害保険料にスポットをあててみましょう。
軽自動車とコンパクトカーの違いとは

一口に軽自動車とコンパクトカーと言われても、どのような違いがあるのか分かりにくいところもあるのではないでしょうか。
まず、車両の大きさを下記の図表で確認してみましょう。
| 軽自動車 | コンパクトカー | |
|---|---|---|
| 全長 | 3.40m以下 | 4.70m程度 |
| 全幅 | 1.48m以下 | 1.70m程度 |
| 全高 | 2.00m以下 | 2.00m程度 |
| 排気量 | 660cc以下 | 2,000cc以内 |
全国軽自動車協会連合会と日本自動車販売協会連合会を基に作成
©Ecompany All rights reserved
軽自動車の規格は日本独自のもので、戦後の経済復興をねらい、規格が定められました。黄色のナンバープレートが目印の小さな車両です。
乗車定員は4人以下、小回りがきき、街乗りにはとても便利です。ダイハツのタント、スズキのワゴンRやホンダのN・ボックスなど各社様々な軽自動車を販売しています。
コンパクトカーついて、実は明確な規定はありません。いわゆる5ナンバーのサイズで「小型自動車」に分類されます。
コンパクトカーという呼び名は、一つのカテゴリーのようなものです。軽自動車よりも大きく、一般的な普通車よりも小さいという利点があるので、重宝されています。
例えば、ニッサンのノート、トヨタのアクアやホンダのフィットなどがあります。
維持費はいくら?
ここで気になるのは、軽自動車とコンパクトカーの維持費についてです。
自家用乗用車の自動車検査登録制度(通称:車検)は、新車登録から3年後に初回の車検があり、以後2年ごとにあります。
2回目以降の車検で継続使用(13年未満)の条件で軽自動車とコンパクトカーの最低限かかる費用(法的費用)を比較してみました。下記の図表をご覧ください。
車検実施時(2年間)に支払う法定費用
| 軽自動車 | コンパクトカー | |
|---|---|---|
| 自動車税 | 21,600円 (10,800円/年) |
69,000円 (34,500円/年) |
| 自動車重量税(2年間) | 6,600円 | 24,600円 |
| 自賠責保険料(2年間)※1 | 25,070円 | 25,830円 |
| 合計 | 53,270円 | 119,430円 |
※1:沖縄県、離島除く保険料
総務省 地方税制度、損害保険料率算出機構、国土交通省 自動車重量税を基に作成
©Ecompany All rights reserved
自動車税は、自動車の所有者にかかる都道府県税で、自動車の定置場のある都道府県が課税している税金です。
一方、自動車重量税は、自動車の区分や重量、経過年数に応じて課税される税金のことで、車両重量0.5トン毎に税額が増加し、軽自動車の場合は、一定の金額となっています。
また、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、すべての自動車が自動車損害賠償保障法に基づき、加入していなければ運転することはできません。
また、相手の人的補償のみになっているので、車の損傷、自分・搭乗者の補償などには対応しません。
法的費用においては、自動車税、自動車重量税、自賠責保険の3つを合わせると、コンパクトカーは、軽自動車の2倍以上の金額になっています。
ただし、自賠責保険での支払限度額よりも多く損害賠償金を請求される場合があります。そのため、カバーしきれない損害を補償する任意保険に加入する必要があります。
軽自動車とコンパクトカーの保険料の比較
それでは、任意保険の補償内容について、あらためて確認してみましょう。下記の図表をご覧ください。
| 補償内容 | 意味 |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 他人を死傷させてしまった場合、相手方に支払う治療費や慰謝料などが補償される |
| 対物賠償保険 | 他人の車やモノを壊してしまった場合、修理費などが補償される |
| 他車運転特約 | 借りた車を運転中に事故を起こしてしまった場合、契約の自動車の契約内容に従い、自分の保険から優先して保険金が支払われる |
| 人身傷害保険 | 車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷した場合や後遺障害を負った場合に、治療費の実費や、働けない間の収入、精神的損害などが補償される |
| 無保険車傷害特約 | 保険に加入していない車との事故で死亡または後遺障害を負い、相手から十分な損害賠償が受けられない場合、補償される |
| 車両保険 | 事故により損害を被ったり、車両同士の事故に遭った場合など、補償される |
| 弁護士費用特約 | 人身事故や物損事故に遭い、損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用などや、法律相談をする場合の費用を補償される |
©Ecompany All rights reserved
対人・対物賠償保険は、賠償金額が高額になることがあるので、無制限となっている場合が多いです。
その他、事故などにより走行不能となった場合に必要な応急処置費用、レッカーの運搬費用などが補償される「ロードアシスタント特約」などの補償も付加することができます。
実際、軽自動車とコンパクトカーではどのくらいの保険料の差があるのか、下記の条件でシミュレーションをしてみました。
条件:40歳男性、ゴールドカード、無事故、ノンフリート等級7等級(1等級~20等級で表され、新規契約は6等級。
等級が高いほど割引率も高くなります)、年間走行距離5,000km~10,000km、対人・対物賠償保険、他車運転特約は基本補償
1年間の保険料
| 補償内容 | 軽自動車 | コンパクトカー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A社 | B社 | A社 | B社 | ||
| 相手の補償 | 対人・対物 賠償保険 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 自分・搭乗者の補償 | 他車運転特約 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人身傷害保険 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | |
| 無保険車傷害特約 | 2億円 | 2億円 | 2億円 | 2億円 | |
| 車の補償 | 車両保険 | 135万円 | 135万円 | 135万円 | 135万円 |
| 車両保険 (免責金額) |
1回目0万円 2回目10万円 |
1回目0万円 2回目10万円 |
1回目0万円 2回目10万円 |
1回目0万円 2回目10万円 |
|
| 弁護士費用特約 | - | 自動付帯 | - | 自動付帯 | |
| インターネット割引 | 6,000円 | 1万円 | 6,000円 | 1万円 | |
| 証券不発行割引 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |
| 保険料 | 5万2,840円 | 4万7,560円 | 5万6,550円 | 5万1,440円 | |
大手損害保険会社のシミュレーションを基に作成
©Ecompany All rights reserved
A社とB社の違いは、軽自動車もコンパクトカーにおいても、その差は5,000円強です。B社はインターネット申込の割引金額が高く、かつ弁護士費用特約が自動付帯となっているのでお得感があります。
それでは、軽自動車とコンパクトカーの保険料はどれくらい違うのか見てみると、A社とB社ともに軽自動車の保険料はコンパクトカーと比べ安くなっています。
車両の大きさや排気量の違いから、差が出るのは当然かと思いますが、その差は約4,000円程度になっています。2018年1月から大手損害保険会社が保険料を2~3%の引き下げを行っているので、確認するといいでしょう。
任意保険では大きな差がでないため、最終的に注意したいのは、コンパクトカーは車検時に支払う法定費用が軽自動車に比べ割高になっていることです。
トータルの維持費は軽自動車よりも高くなるのは否めません。車を選ぶときは、維持費や保険料も加味しながら、検討してみましょう。